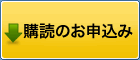二十五歳の派遣社員の男が、歩行者天国の秋葉原で七人を殺した事件。どう受け止めて、どう考えればいいのか、その糸口さえも思い浮かばない気分で、報道を見たり聞いたりする。憤ったり、怒ったり、非難したり…、そんな感情の横に、「どうなってしまったんだろう、どうなって行くんだろう、私たちの社会や国やヒトの世界は」という、ガラスを金属片で引っ掻いた時に出る音を聞くような、神経を逆撫でされる、どうしようもない気持ちがある。
翌日の読売新聞一面「編集手帳」の一文を読んで、気分はますます深みに落ち込んで行く。一部を引用する。
「世の中が嫌になったのならば自分ひとりが世を去ればいいものを、『容疑者』という型通りの一語を添える気にもならない」
受験競争からの脱落、親との断絶、派遣社員という不安定な職、友達がいない、彼女がいない…、容疑者の男の「暗」や「負」や「苦」の部分を幾つ数え上げようが、彼が犯した凶行を説明できるわけでも、弁護できるわけでもない。甘ったれるな、とも思う。だが、だが、「自分ひとりが世を去ればいいものを」のセリフは、仮に、犯行に及ぶ前に二十五歳の男から計画を聞かされた時、諭すために費やすたくさんの言葉の一つとして、反語・アイロニーとして、使うべきものではないのか。少なくても、七人の生命が奪われ、十人が重軽症を負った事件が起こった後に、常識人が、キレた調子で、感情を煽る文脈として吐き出す言葉ではないだろう。
逮捕された直後の、返り血を浴びた二十五歳の犯人の映像を何度も見ながら、考える。個々人が持ち合わせている特技や能力や持ち味、創造性とは全く関係なく、「頭数」の一人として扱われるであろう派遣社員という「職業」に就いた経験は、ない。だが、転職を何度も繰り返した体験から、職場で自分の居場所を確保するのが、どれほど大変か、不安か、気持ちがさいなまれるかは知っている。社会や組織の中で、自分が存在する意義、役に立っているという実感、関係を持っているという安心感がない環境で、どうやって精神の安定が保てるのだろう。経済効率追求の中から生み出された「派遣社員」という新職業が、この事件の底にある気がしてならない。枕はここまで。
五月二十七日付の本欄「声のブッポウソウが嵐山を去ったわけ」に関して、妙齢の女性らしき読者から手紙が届いた。「ちょっと早めの暑中見舞いを兼ねまして」との便り。紹介する。
――子どもの頃、実家が農家で、山に近かったものですからブッポウソウ(正体はコノハズクですよね)の声はよく聞きました。五月頃から、年によっては七月の終わりまで、日暮れとともに鳴き始めます。いわば日常のことですから、それほど気に留めていたわけではありませんが、子ども心に「いい鳴き声だなぁ。夏が来たなぁ」と感じていたのをよく憶えています。もう半世紀以上昔のことです。
嵐山でブッポウソウが鳴かなくなったという話、初めて知りました。その理由が、緑町にできた大きなショッピングセンターの照明だとか。夜に行動するコノハズクは、暗いところが好きなんでしょう。嵐山を追われたコノハズクさんは、どこかに、夜になれば暗くなる棲みよい森を見つけられたかと心が痛みます。
「コンビニエンスストア一店舗が一日に消費する電気量は、平均的な一般家庭の二カ月分にあたる」ともありました。コンビニエンスストアを利用することはほとんどありませんし、忙しい現代人にとっては便利なお店なのでしょうが、洞爺湖サミットのテーマが地球の環境、温暖化という時代に、二十四時間照明やら冷蔵庫やらに電気をふんだんに使うお店が街中にある社会が果たして許されるものか、年寄りの冷や水と知りつつ頭を傾げてしまいます。
戦前の生まれで、ものがない時代に育ち、結婚して四人の子どもを育てましたから、気持ちの中に「こんなにものが豊かな生活が、そうそう長続きするはずはない」という思いがいつもあった気がします。ですから、最近になってガソリンの値段が急に高くなったり、食料品が軒並み値上げされたりしても、「やっぱりね」と感じたりします。
過ぎる、というのはいけませんね。豊か過ぎたり、便利過ぎたり、大き過ぎたり、安過ぎたり。おかしな天候も、次々に起きる凶悪な事件も、何もかもが「過ぎた」社会が引き起こしているような気がしてなりません。
余計なことを長々と書いてしまいました。いつも楽しみに読ませていただいています。ますますのご健筆を。